月報「わっぱ」 2015年4月(No.401)
御料局三角点の意味
昨年の10月初め、私は「御料局三角点」に出合った。南アルプス深南部の鶏冠山(2204m)に池口川登山口から登った時、山頂に続く主稜線上のマナイタ平に古い石柱。「御料局三角点」の文字がぼんやり読み取れた(写真①)。8月初めの南ア山行でも、易老岳の頂上と光岳頂上でも見届けた。御料局三角点を現認したのは初めてだった。

明治維新政府は旧藩管理の林野を官林とし国有化した。所管は農商務省だ。さらにその中から、明治23年(1890)までに皇室財産として移管させたのが「御料林」だ。所管は宮内省御料局。最大時には全国に360万㌶あったと言われ、北ア、南アの山域、木曽、岐阜県の裏木曽の山林は多くは御料林だった。
明治中期、御料局は御料林の境界や面積把握のため、近代的な三角測量を始めた。未知の山岳高地の御料林をくまなく踏査し、設置したのが御料局三角点だ。一方、陸軍陸地測量部も同じころ三角測量を始めたが、御料局のほうが先行していたようだ。陸地測量部が御料局三角点の成果をそのまま採用した三角点もあった。御料局測量官は陸地測量部が本格的な三角点測量を始める前に、南アや中アに分け入り三角測量をした。日本の登山史に残した役割は陸地測量部に劣らぬものがあった。だが、その功績の多くは忘れ去られた。
私が昨年、触れたマナイタ平、易老岳、光岳の御料局三角点は上条武著「孤高の道しるべ」によると明治33年に設置された。110余年前に道なきやぶ山や懸崖の山頂を極めた測量官たちの苦闘の結晶であった。ただ、御料林の存在は地元民や自治体との間で紛争や論争を生んだという側面もあった。
(鈴木 正昭)

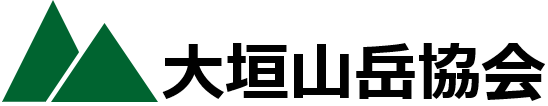



コメント